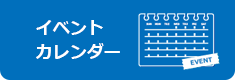本文
幼児教育・保育の無償化について
1.概要
令和元年10月1日から、主に3歳児から5歳児を対象として、保育所、認定こども園、地域型保育事業、幼稚園などの保育料が無償になります。(一部条件あり)
無償化の対象範囲や金額は、年齢、利用する教育・保育施設などの種類、保育の必要性の有無、住民税の課税状態により異なりますので、詳しくは下記をご確認ください。
※ 無償化が始まった後も、既存の軽減(第2子・第3子の多子軽減)は継続します。
2.無償化の内容
(1) 保育所、認定こども園(2・3号)、地域型保育事業を利用する子どもたちの無償化
- 3歳児から5歳児の子どもは、保育料が無償になります。
- 住民税非課税世帯の0歳児から2歳児の子どもは、保育料が無償になります。
(注)無償化の対象外となる費用
- 実費として集めさせていただく通園送迎費、給食の食材料費、行事費、教材費、延長保育料などは、引き続き保護者の負担となります。
- ただし、年収360万円未満相当世帯の子どもと、第3子の子どもについては、副食費(おかず・おやつ等)が免除されます。
※第3子…小学校就学前児童から数えて第3子以降の子ども(認可保育所・認定こども園(保育利用)・地域型保育事業におけるカウントの仕方)
(2)認定こども園(1号)、幼稚園を利用する子どもたちの無償化
- 3歳児から5歳児の子どもは、保育料が無償になります。
- 満3歳(3歳になった日から次の3月31日まで)の子どもは、保育料が無償になります。
※新制度未移行幼稚園については、月額25,700円を上限に無償化
(注)無償化の対象外となる費用
- 実費として集めさせていただく通園送迎費、給食の食材料費、行事費、教材費、延長保育料などは、引き続き保護者の負担となります。
- ただし、年収360万円未満相当世帯の子どもと、第3子の子どもについては、副食費(おかず・おやつ等)が免除されます。
※第3子…小学校3年生から数えて第3子以降の子ども(認定こども園(教育利用)・幼稚園におけるカウントの仕方)
(3)認定こども園(1号)、幼稚園の預かり保育を利用する子どもたちの無償化
- 「保育の必要性の認定を受けた」3歳児から5歳児の子どもは、月額11,300円を上限に、預かり保育の利用料が無償になります。
- 「保育の必要性の認定を受けた」住民税非課税世帯の満3歳の子どもは、月額16,300円を上限に、預かり保育の利用料が無償になります。
※預かり保育の利用日数に応じて1日あたり450円、月額11,300円(16,300円)を上限に無償化
※市から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。手続き方法については、追ってお知らせいたします。
(4)認可外保育施設などを利用する子どもたちの無償化
- 「保育の必要性の認定を受けた」3歳児から5歳児の子どもは、月額37,000円を上限に利用料が無料になります。
- 「保育の必要性の認定を受けた」住民税非課税世帯の0歳児から2歳児の子どもは、月額42,000円を上限に利用料が無料になります。
※認可外保育施設など…一般的な認可外保育施設、ファミリー・サポート・センター事業、一時預かり事業、病児保育事業 等
※市から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。手続き方法については、追ってお知らせいたします。
(5)障害児通園施設を利用する子どもたちの無償化
就学前の障害児の発達支援を利用する3歳児から5歳児までの子どもは、利用料が無償になります。
※保育所、認定こども園、地域型保育事業などと、併せて利用する場合は、ともに無償化
| 3歳から5歳児 | 0歳児から2歳児 | ||
|---|---|---|---|
| 保育の必要性 の認定あり |
保育の必要性 の認定なし |
保育認定がある 住民税非課税世帯 |
|
| 保育所 | 無償 | 無償 | |
| 地域型保育事業 | 無償 | 無償 | |
| 認定こども園 | 無償 | 無償※2 | 無償 |
| 幼稚園※1 | 無償 | 無償※2 | |
| 幼稚園(認定こども園) の預かり保育※3 |
利用日数に応じて、 月額11,300円まで 無償 ※4 |
ー | |
| 認可外保育施設など※3 | 月額37,000円まで無償 | ー | 月額42,000円まで無償 |
※1新制度未移行幼稚園については、月額25,700円まで無償化
※2認定こども園(1号)、幼稚園については、満3歳から無償化
※3「保育の必要性の認定」を受けた子どもが対象
※4住民税非課税世帯の満3歳の子どもは、最大月額16,300円までの範囲で無償化
3.関連リンク
幼児教育・保育の無償化(こども家庭庁)<外部リンク>
4.問い合わせ先
(本庁)子育て支援課 保育係 Tel:0880-34-1780
(総合支所)西土佐保健分室 Tel:0880-52-1132